「自院のウェブサイトで、もっと患者さんに役立つ情報を発信したい」 「ヘルスケアサービスの信頼性を高めるため、専門的な記事を増やしたい」このようにお考えの、医療機関の先生やヘルスケア企業の担当者様も多いのではないでしょうか。
質の高い医療記事は検索エンジンからの評価が高くなり、読者に届きやすくなるとともに集患や集客に寄与します。ただ、生成AIが急速に発展している今でも、特に医療分野のコンテンツマーケティングでは、その専門性と正確性から記事制作のハードルが非常に高くなっています。
ここでは、医療という専門領域で高品質な記事(コンテンツ)を制作するためのポイントから、外注する場合の信頼できる外注先の選び方、制作フローまでを網羅的に解説します。
※注:このコラムでいう記事とは、主に医療機関や企業が独自で作るウェブサイトやオウンドメディア掲載のものを想定しています。
目次
質の高い医療記事とは

まず、「質の高い医療記事・医療コンテンツ」とはどのようなものでしょうか。
医療記事は、何らかの病気で悩んでいる患者さんやご家族、また病気を予防したいと考えている一般の方が読者です。こうした読者を想定したときに重要なのは、病気や健康のことで不安を抱える読者の心に寄り添い、正確で分かりやすい情報を提供することで、その不安を解消し、安心感と信頼を与えることです。
読者は専門的な知識を学びたいわけではなく、「自分のこの症状は大丈夫だろうか?」「どんな治療法があるのだろう?」といった切実な悩みの答えを探しています。正しい情報であることはもちろんですが、そうした悩みに最応え、次の行動(受診や相談など)を後押しできる記事こそが、本当に価値のある医療記事と言えるでしょう。
SEOに強く、質の高い医療記事を制作するために
せっかく質の高い情報を発信していても、それが読者に届かなければ意味がありません。その意味でSEOは重要ですが、幸いなことにGoogleは「質の高いコンテンツ」が最優先で上位表示されるようにしています。
Googleなどの検索エンジンで上位表示され、多くの読者に読まれる質の高い記事制作のためには、医学的な正しさに加えて、いくつかの専門的な要件を満たす必要があります。制作するために不可欠な5つの要素を解説します。
1. 疾患や診療に対する経験値や理解
表面的な知識の羅列ではなく、実際の臨床現場での経験に基づいた深い理解が記事の質を左右します。
例えば、同じ疾患について解説するにしても、患者さんがどのような点に不安を感じ、どのような言葉で説明すれば安心するのかを理解しているかで、記事の説得力は大きく変わります。
医療機関が医師の監修に基づいて独自で制作する場合には、こうした要件は満たしやすいと言えます。あるいは「医療現場や業界での経験を活かしたライティング」ができる専門家が執筆・編集・監修に関わることが理想的です。
2. 薬機法・医療広告ガイドラインの知識と遵守
医療コンテンツを制作する上で、薬機法(旧薬事法)と医療広告ガイドラインの遵守は絶対条件です。
薬機法:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律のことで、未承認の医薬品や医療機器の広告などを厳しく規制しています。医療広告ガイドライン:患者の不利益になるような不適切な広告を規制するためのガイドラインです。「広告」となっていますが、ホームページやLP、SNSも規制には含まれています。「ビフォーアフター写真掲載時の条件」や「誇大表現の禁止」など、具体的なルールが定められています。
これらの法規制を理解せずに記事やホームページの中身を作成すると、意図せず違反してしまうリスクがあります。違反した場合は行政指導の対象となるだけでなく、医療機関や企業としての信頼を著しく損なうことになりかねません。
3. コンテンツマーケティングやSEOの知識
質の高い記事こそがSEOに強いことは間違いありませんが、そのためには、検索ユーザーがどのようなキーワードで情報を探しているのかを分析し、その検索意図に応えるコンテンツを企画・制作する「コンテンツマーケティング」の視点とSEO(検索エンジン最適化)の知識が不可欠です。
正しい医学知識とSEOの知識、この両輪が揃って初めて、検索上位表示と集患・集客という成果に繋がります。
4. E-E-A-Tを担保する
E-E-A-T(Experience - Expertise - Authoritativeness - Trustworthiness)とは、Googleがコンテンツの品質を評価するための重要な指標です。特に、人々の健康や財産に大きな影響を与えるYMYL(Your Money or Your Life)領域である医療分野では、このE-E-A-Tが極めて厳しく評価されます。
- Experience(経験) そのトピックに関する実体験や経験があるか。
- Expertise(専門性) そのトピックに関する専門知識を持っているか。
- Authoritativeness(権威性) その分野の第一人者として広く認められているか。
- Trustworthiness(信頼性) 情報が正確で信頼できるか。
医師や各分野の専門家が執筆・監修に関わり、誰がその情報を発信しているのかを明確にすることが、E-E-A-T、特に信頼性を担保する上で最も重要な施策となります。
5. 本数を作ればいいというものではない
医療分野のコンテンツマーケティングでは、記事の量よりも質が圧倒的に重要です。
質の低い記事を量産しても、Googleからの評価は得られず、読者の信頼を勝ち取ることもできません。むしろ、1本1本の記事にコストと時間をかけ、読者の悩みに深く応えるコンテンツを丁寧に作り上げることが、結果的にウェブサイト全体の評価を高め、安定した集客に繋がります。
医療記事の外注先を選定するときのポイント
専門性の高い医療記事の制作を外部に依頼する場合、どのような基準でパートナーを選べばよいのでしょうか。ここでは、失敗しないための4つの選定ポイントをご紹介します。
1. 医療分野の知識や経験が豊富かどうか
制作会社やライターが医療分野に特化しているか、あるいは豊富な実績を持っているかを確認しましょう。
医療業界の慣習や専門用語、そして何より患者さんの心理を理解しているパートナーでなければ、質の高い記事制作は望めません。どのような経歴のディレクターやライターが制作に関わるのか、過去にどのような領域の記事を作成してきたかを確認することが重要です。
2. 医師や専門家のインタビュー経験が豊富かどうか

医師や専門医の先生にインタビューして記事を作成する可能性がある場合、インタビュアーのスキルが記事の質を大きく左右します。
多忙な先生方の貴重な時間を無駄にせず、専門的な話を分かりやすく引き出し、読者に伝わる言葉に変換する能力が求められます。ライティングはできるがインタビューはできないというライターが実は多くいます。インタビュー経験が豊富な会社であれば、事前の質問リストの準備から当日の進行、原稿作成までスムーズに進めてくれるでしょう。
3. 必要に応じて診療ガイドラインや医学論文が参照できるか
情報の正確性と信頼性を担保するため、最新の診療ガイドラインや信頼できる医学論文をリサーチし、それらを基に執筆できるスキルや体制があるかは非常に重要なポイントです。
他のクリニックのホームページや他社サイトのみを参照して執筆するところも少なくありません。表面的な情報だけでなく、学会やガイドライン、論文などの一次情報を参照し、エビデンス(科学的根拠)に基づいた記事を作成できるかどうかは、制作会社の専門性を見極めるポイントとなります。
4. 医師など専門家の監修協力を得られる体制があるか
E-E-A-Tを確保し、読者からの信頼を得るために、必要に応じて医師や専門家による監修体制が組めるかも重要です。
医療機関が制作する場合は、組織内の医師に監修いただければ問題ないでしょう。製薬会社やヘルスケア企業などで、自社で監修医を手配できない場合は、制作会社側で各診療科の専門医ネットワークを持っており、監修を依頼できる体制が整っているとE-E-A-Tを確保した記事制作に有利です。監修者の顔写真やプロフィールを記事に掲載できるかも、合わせて確認しておきたいポイントです。
生成AIで医療記事は作れるか
近年、急速に進化している生成AIですが、「生成AIを使って医療記事を作成できるか?」という問いに対して、答えは「完全には難しい」です。その理由は以下のとおりです。
■情報の正確性が保証できない
AIが生成する情報は、世の中に公開されている数多のウェブサイトを学習したデータに基づいたものであり、常に正しいとは限りません。古い情報や誤った情報が含まれている可能性があり、人命に関わる医療分野では致命的な欠陥となります。
■E-E-A-T(特に経験)を担保できない
AIには実際の臨床経験や患者さんとの対話経験(Experience)がありません。そのため、現場でしか得られないような読者の不安に寄り添うような文章を作成することは困難です。
■倫理的リスク
AIが生成した誤った情報によって読者に健康被害が生じた場合、その責任は情報の発信者である医療機関や企業が負うことになります。
生成AIは文章の要約や構成案の作成など補助的なツールとしては有用です。医療+コンテンツマーケティングの専門知識と経験を持つ人間が、内容をわかったうえで使用すれば、効率を高めつつ質の高い記事制作にも役立つでしょう。
医療分野の制作実績と導入事例
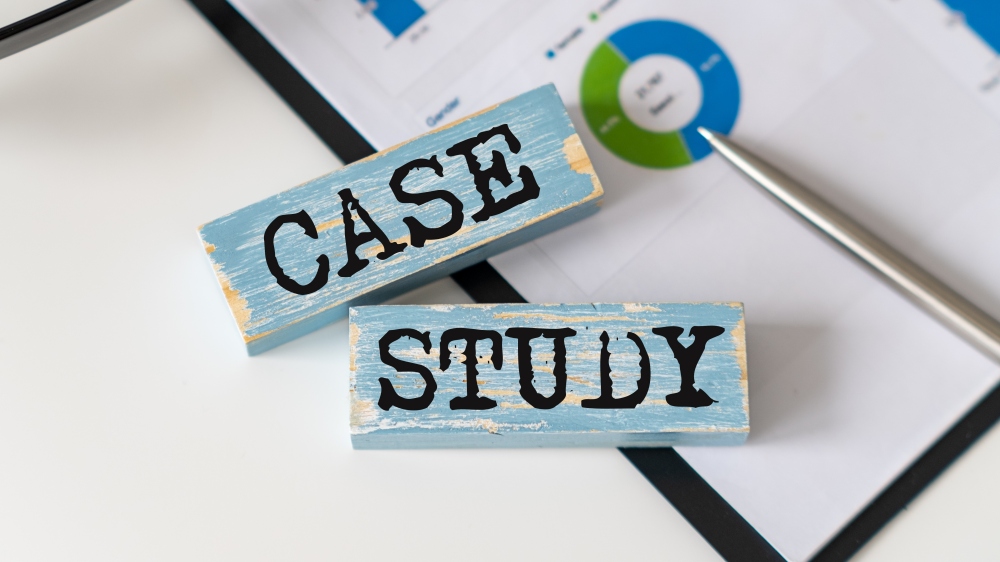
ここでは、弊社が手がけた医療分野における記事制作の事例をいくつかご紹介します。
■クリニック・病院のコラム記事事例
- クライアント:名古屋市内のクリニック様
- 診療科目:内科を中心とした外来診療、および人間ドック・健康診断
- 課題 都市中心部に立地するため競合も多い中で、特に人間ドックへのお問い合わせ、利用者を伸ばしたい。
→【事例紹介】クリニック様ホームページのSEO対策(医療コラム記事制作)
■製薬メーカー(医療用医薬品)の疾患啓発コンテンツ制作事例
- クライアント:大手外資系製薬メーカー様(医療系広告代理店様からの依頼)
- リクエスト: 対象となるがんの治療や療養生活についての幅広い知識・理解、制作実績。制作ボリュームが大きく、動画や患者体験談など多岐にわたるコンテンツを制作するため、ライターや映像制作会社も含めたディレクションも頼みたい。
→【事例紹介】製薬メーカー(医療用医薬品)様 がん患者・家族向け情報サイトコンテンツ制作
■製薬メーカー(OTC医薬品)のブランサイトSEOのための医師監修記事制作事例
- クライアント:大手国内製薬メーカー様(広告代理店様からの依頼)
- 課題:競合製品のサイトのSEOが強く、自社サイトが埋もれてしまっているため改善したい。医師監修の記事を制作したい。
→【事例紹介】製薬メーカー(OTC医薬品)様 ブランドページのSEO対策(医療記事制作)
外注して制作する場合の主な流れ
医療記事・医療コンテンツを外注で制作する場合の基本的な流れを、弊社の例でご紹介します。
ステップ1:お問い合わせ・無料相談
ステップ2:SEOキーワード調査・テーマ企画提案
ご契約後、貴社のターゲットや目的に合わせ、施策に効果的なSEOキーワードの調査・選定を行います。その上で、ユーザーの検索意図を深く分析し、具体的な記事テーマ案をご提案します。
ステップ3:構成案作成・執筆
ご提案内容にご納得いただけましたら、医療分野専門のライターが構成案を作成し、執筆を開始します。必要に応じて、貴院の先生方へのインタビューも実施いたします。制作した原稿を校正・校閲いただき、必要な場合は修正を行います。弊社にご協力いただいている医師による監修チェックもご提案できます。
ステップ4:校正・納品
すべてのチェック・修正が完了し、クライアント様より校了のご了解をいただたら、記事を納品させていただきます。
ポイントは、SEOキーワード調査・テーマ案作成の質(ユーザー理解)と、初稿の品質です。せっかくコストをかけて外注しても、出てきた原稿が医療従事者から見て違和感の多い原稿であれば、手直しの手間が大きくなり、何のために外注しているのか分からなくなってしまいます。
まとめ:医療記事制作は正しい医学知識とSEOの知識の両輪が必要
医療・ヘルスケア分野の情報発信では、正確性と専門性に加え、読者の心に届くわかりやすさが求められます。専門知識をもとにした記事は、信頼を高めるだけでなく、検索エンジンからの評価向上や集患・集客にも直結します。だからこそ、医療現場の理解とSEOの知識を兼ね備えたパートナー選びが重要です。
株式会社うぇるなすでは、医療分野・ヘルスケア分野に特化して、コンテンツマーケティングやSEO対策、ウェブサイトやコラム記事などのコンテンツ制作をご支援しています。医療とSEOの両方が分かるマーケター&ディレクター、医療系出版社や元看護師・薬剤師などのライター陣・編集スタッフにより、高品質な医療コンテンツを制作。貴院・貴社の想いを正しく伝え、患者・生活者から信頼される情報発信を支援します。
検討段階でも、お問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。
この記事を書いた人
笠井 篤(株式会社うぇるなす代表取締役・SEOマーケター)

医療系上場企業に16年在籍し、患者向けマーケティングを担当。 全国のがん専門医の先生方の協力を得ながら治療や療養生活に関する情報発信や、医療機関のWEB制作・コンテンツマーケティング、SEO対策などを支援する。その最中に家族ががんになり、闘病を経験。
医療機関や企業と患者さんやユーザーをつなぐための質の高いコンテンツが重要という思いから独立し、医療・ヘルスケア・製薬分野に特化してコンテンツマーケティング・SEO対策、WEB制作を支援するうぇるなすを設立。
